第6回 山谷佑介 “Doors” 帰国報告会 “I CAME BACK HOME 2020” at pulp
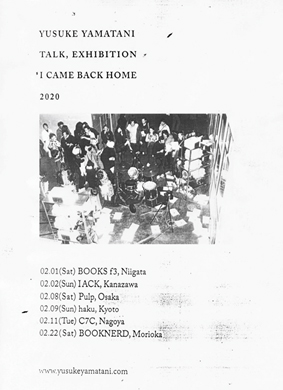
「知らない土地で言葉の通じないところでやりたかった。」

2020年2月8日(土)写真家 山谷佑介は大阪pulpで開催された自身のヨーロッパツアー「Doors」の帰国報告会「I CAME BACK HOME 2020」の冒頭でそう語り始めた。
2017年に話は戻る。当時山谷は初めての子供をもうけたことで自身を取り巻く環境が大きく変化した。母親は体の変化を通じて母性を意識し徐々に母となっていくが、父親はいつ父になればいいのかがわからなかった。夜泣きをする子供に対して父親が出来ることは少なく、戸惑い、夜中に出歩くことが多くなった。深夜の住宅街を彷徨い歩きながら時間をつぶす日々、ふとこの住宅の中を覗いてみたいという衝動にかられる。一つ一つの住宅の中にはいろんな生活があり様々な人間が暮らしている。でも自分はそれを外からは容易に覗くことは出来ない。どんなにカメラを駆使しても分厚いコンクリートの壁をすりぬけて中を覗き見ることは出来ないからだ。しかしカメラを向けることで何かを写し取ることが出来るかも知れない。そう思い立った山谷は、赤外線カメラを用意して深夜の住宅にカメラを向けはじめた。そうして出来上がったのが「Into the Light」である。写真集の巻頭で山谷はこう記している。
「深夜の住宅街をさまよい、歩いた。
他者の領域に足を踏み入れ撮影することは、自分の世界との隔たりを感じさせながらも、
私に妙な居心地の良さを感じさせるのだった。」
|
|
Into the Light | 山谷佑介
|
「居心地の良さ」とは言い換えると、撮る者と撮られる者との間にある緊密な共犯者感覚と言うものだろうか?それはいつ警察に通報されるかも知れないという不安定な感覚であり、撮っているのはこちら側でも実はこちらも誰かに見られているかも知れないという緊張感である。山谷はそれを「家からの視線」と表現する。それは森の中をひとり歩いている時に感じるザワザワする感じに似ているとも。さらにもっと以前の記憶に戻り、初めてカメラの仕事のもらった時の失敗談に移る。その時は被写体に向けたカメラの露出を5段階も間違えて後から青くなったという話だったが、あの時感じた緊張感や切羽詰まった思いはもう二度としたくはないが、ただもう一度あの時のような自分には立ち返りたいと思う時がある。慣れから解放されたい。そんな思いが最初の一文にたどり着くのである。
写真とパフォーマンス 無意識の領域 京都グラフィーでの挑戦
京都グラフィー2018で山谷は「ギャラリー山谷」と名付けた真っ暗な空間にドラムセットを組んだ。長くバンドでドラマーをやっていた経験があり、ドラムを叩くことに関してはほぼ無意識でも体は動いた。そしてシャッターを押すという行為を無意識の領域に押し込む方法として、ドラムセットのスネアという部分にセンサーを仕込んで、それが振動することでセンサーが働きシャッターを押すという仕組みを考えた。3台のカメラでドラムセットの前に座る自分を狙い、撮影された画像は順次パソコンに転送され、あらかじめプログラミングした通りに数台のモノクロプリンターに振り分けてプリントする。パフォーマンスの間中もプリンターからは無数のモノクロのプリントが排出されていく。パフォーマンス中もプリントという成果物を見せることで、あくまでも写真を撮るという行為とパフォーマンスのどちらの要素も同時に満たし、かつ生産されたプリントをオーディエンスが選択して持ち帰るという一連のプロセスまでを山谷自身も知らぬ無意識の領域で完結させるという挑戦だったのである。

この辺りから質問をはさみながら進行される。
ツルノユカギャラリーでの展示。「MY YAMATANI」という試み

京都グラフィーでのパフォーマンスの後、東京に戻った山谷はツルノユカギャラリーで京都グラフィーでのパフォーマンスをまとめた展示を開催した。展示の中で山谷は自分がセレクトしたプリントをよく見てみると実は体裁の良いものばかりを選んでいることに気が付く。そしてそれは山谷の新しい気付きとなり、「パフォーマンス会場から持ち帰ったプリントには何が写し取られているのか?」、「何を選び、どうやって飾られているのか?」そんなことが気になり始めた。それは後に「あなたの家にいるリトル山谷を写真に撮って送ってもらう」というWANTED MY YAMATANIというアイデアにつながる。

ヨーロッパツアーという新たな挑戦
新たな挑戦の場を模索していた山谷は、次第にパフォーマンスの場を海外に求めたいという欲求がわいていた。オランダ アムステルダム、毎年9月に開催されるUnseen Photo Fairのように写真家に寛容な街なら、言葉が通じなくてもやっていけるのではないだろうか?当時ギャラリーのオーナーである鶴野さんにそんなことを話している中で、海外挑戦費用の負担として助成金などはどうだろうと相談をしたところ、「山谷君らしくない、クラウドファンディングでもやってみたら」と提案される。その後キックスターターというサイトでなんとか100万円を集めたが、後に全然足りていないことに気が付く。

ヨーロッパツアーの準備
ツアーを始めるにあたり少しでも費用を圧縮するために、まずはドラムセットをヨーロッパで借りることの出来るところを探した。ちょうどロンドンを活動の拠点としている知り合いのバンド「ボーニンゲン」が、9月一杯はツアーをやらないということがわかりあてが付いた。ロンドンでレンタルしたワゴン車にドラムセットを積み込んで、ポーランドを皮切りに一筆書きでヨーロッパを一周することにした。同行する人としてプログラムを担当してくれたエンジニアの山森君にお願いすることになった。
メカニックな話
スネアを叩くと振動センサーが反応してシャッターが切られる。ここまでを湘南に住んでいるメカエンジニアのおじさんに頼んで作ってもらった。大手の業者にお願いすると数十万円にもなるメカだが、運よくネットで探したおじさんにお願いすると数万円で可能だった。次に3台のカメラが反応しパソコンに画像が送られる。パソコンはその画像をいくつかあるモノクロプリンターに振り分けてプリントする。そのあたりを山森君にお願いした。モノクロプリンターは同じ機種ばかりを大量に販売している業者をオークションサイトで探して格安で購入した。しかし手にしてみるとどれもこれもプリントに様々な種類の筋が入る。結局それも無機質な表現となって今では良かったと思っている。ちなみにヨーロッパ同行をお願いした山森君は、なんと今回が初めての海外旅行にもかかわらず、ワゴン車でヨーロッパ一周をすることになるというとんでもない海外デビューになったわけだが、パスポートは持ってはいたが身分証明書替わりに使っていたぐらいで、実に自動車運転免許も持っていなかったということである。
友人の一言
ある時パフォーマンスを見てくれた友人がおもしろいことを口にした。真っ暗の中でプレーヤー(山谷)がドラムを叩き、それに反応し瞬時にフラッシュがたかれ撮影されるのだが、オーディエンスはその一瞬だけしかプレーヤーを見ることが出来ない。カメラがプレーヤーを撮る瞬間だけ、オーディエンスも同じようにプレーヤーを瞼に焼き付けることが出来る。つまりはオーディエンスの瞼はカメラのシャッターと同じと考えると、パフォーマンス自体が実は写真的なのだと。
なぜDoorsか?
オルダス・ハクスレー著「知覚の扉(The doors of perception )1954年」、幻覚剤によるサイケデリック体験の手記と考察の中で、ウィリアムブレークに言及している。しかしドラッグもないこの世の中でドラッグも使わずに無意識のところまでいかにして行けるのかと考える内にDoorsでいいのではないかとひらめいた。アメリカのバンド、THE DOORSにも少し影響を受けている。
アメリカでやりたいか?と言う質問に対しては、
いつかアメリカでやりたいと思っている。と山谷は答えた。

ベルリンでのパフォーマンスでのこと
アートベルリンが開催されている会場に隣接する駐車場で、ゲリラ的にパフォーマンスをやろうということになって近くでスタンバイをしていた。いざと言う時になって首尾よくドラムセットを組みパフォーマンスを始めることが出来た。次第に人も集まり、何とか15分ほどのパフォーマンスを最後までやりきって倒れ込んでいると、人ごみの中から係員がやって来てひとしきり怒られた。ずっと前からそこにいて最初の時点から気が付いていたのにもかかわらず、パフォーマンスが終了したのを見計らって早く撤収することを促したのである。見ている聴衆が興ざめすることが無いようにとの計らいか、無法者であってもアーティストに対しての敬意なのか、ベルリンの土地が持っているアートへの理解を感じずにはいられなかった。それは小さい頃からアートに慣れ親しんでいるベルリンならではことなのだと山谷は理解した。あとでイギリスの友人にその話をすると、ロンドンではそんなことは絶対許されない。それは世界一監視カメラが多いと言われるほどロンドンは監視社会だからだと言われた。パスが無ければすぐにつかまるとも。
ヨーロッパツアーの感想

ヨーロッパツアー中は3台のカメラの内2台は自分に向けて、残りの1台は回転し聴衆の顔も撮影出来るように改良した。オーディエンスは多い時には80名ほどいる時もあり、見ず知らずの東洋人のパフォーマンスに足を止めて見てくれることに興奮した。オーディエンスとの掛け合い。ライブでいうコールアンドレスポンスのようなやりとり。そして自ら気にいたモノクロプリントを探し、手に取って持ち帰る姿に歓喜を覚えた。
スネアで作るフォトグラム

京都グラフィーでも行った手法だがスネアで作るフォトグラムを、今回のツアーではすべての会場でスネアのヘッドを変えて制作してみた。ヘッドに光にあてて透けてくる光をフォトグラムという手法で印画紙に焼き付ける。今そこにある工業製品を使うことで何も加工されていないrowなものを表現したかった。出来上がったものを見ると地球のようにも見えるし、月のクレーターのようにも見えた。
新しい写真集について

テーブルの上に山積みにしてあるプリントはツアー中のパフォーマンスを映したデータを、日本に戻って来てから新たにプリンターを使って焼き直したものである。気に入ったものがあれば持って帰ってほしい。そして、新しい写真集は現地でプリントしたものをまとめたものにしたいと思っている。それはクラウドファンディングで応募してくれた人と今回賛同してくれた人限定で制作するものになるだろう。
ツアー中の事件

ツアー中、毎日のように何か事件は起こるが、ある国では朝起きたら車が無いということもあった。もちろん警察に持って行かれていたので後日罰金を払うハメになり痛い出費となったが、一番覚えているのはやっとツアーも終了してドラムセットと車を返そうとイギリスに入国する税関でのこと。二人で熱いねーとか言いながら車で待機していると、税関職員がやって来て、パスポートを見せろと言ってきた。1か月もの間ヨーロッパ中を旅する二人連れ。車内にはたくさんの荷物。どう見てもあやしいらしく「何をしてきたんだ」と聞かれる。とっさに日本人らしい昔からの教えに従って「観光です」と答えたが。それがどうも良くなかったようで、上席の職員にどうも不審な奴がいることを告げられたらしく、さらに人数を増やしてワゴンの荷物を調べ始めた。これはまずいと思って、とっさにパソコンを取り出しパフォーマンスを撮影した動画を見せた。しばらくするとようやくこの片言の英語を話すあやしい東洋人がこの一か月間ヨーロッパ各地で何をやって来たのかが理解できたようで、さっきまで犯罪者のように見ていた目つきがごろっと変わって、「こいつすごいことやってるぜ」みたいな雰囲気に変わり無事に税関を通過することが出来たのである。このパフォーマンスの誰でも見ればわかるというキャッチ―さ。そこには言語など関係しないということがよくわかる事件であったと山谷は語った。

その後山谷は今現在進めていることや今後のことを話して、あと残りの会場のPRをして会を締めくくった。山谷の挑戦はこれからも続いていく。
※すべての記事は写真家 山谷佑介さんとpulpギャラリスト 田窪直樹さん、あとは参加者の皆様の質問などを聞き書きして再構成しています。またすべての写真は該当する場所で撮影しています。
